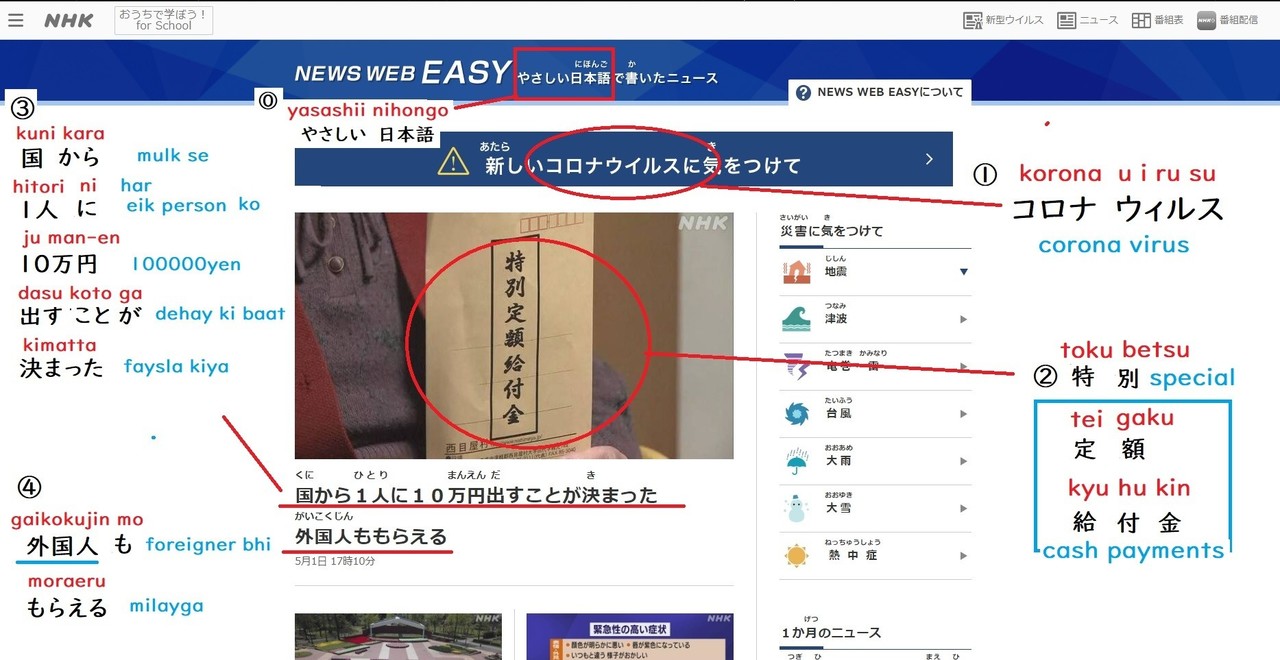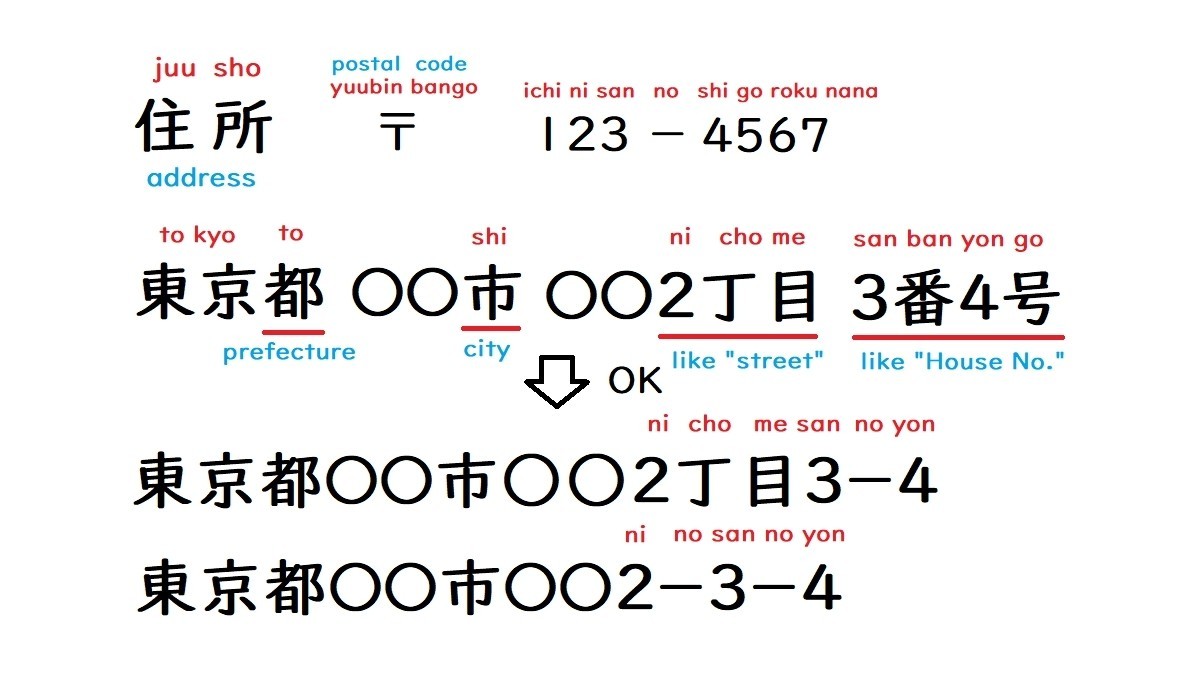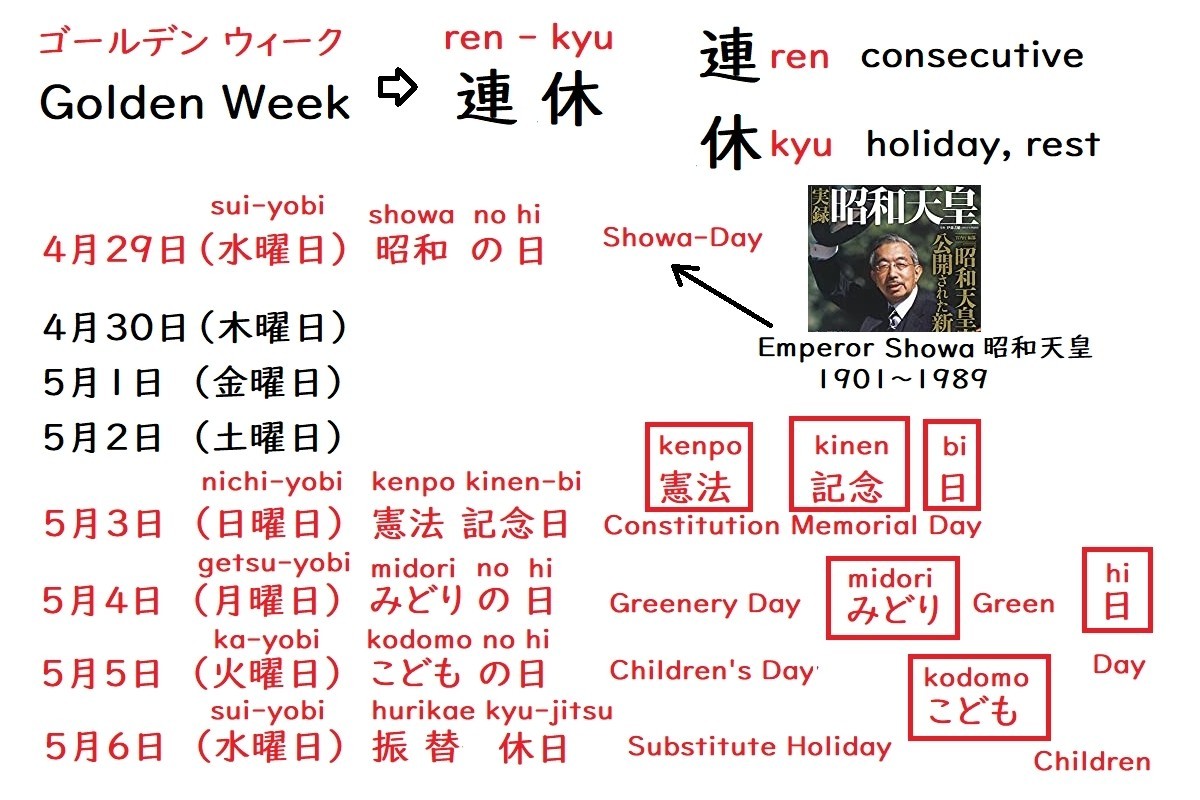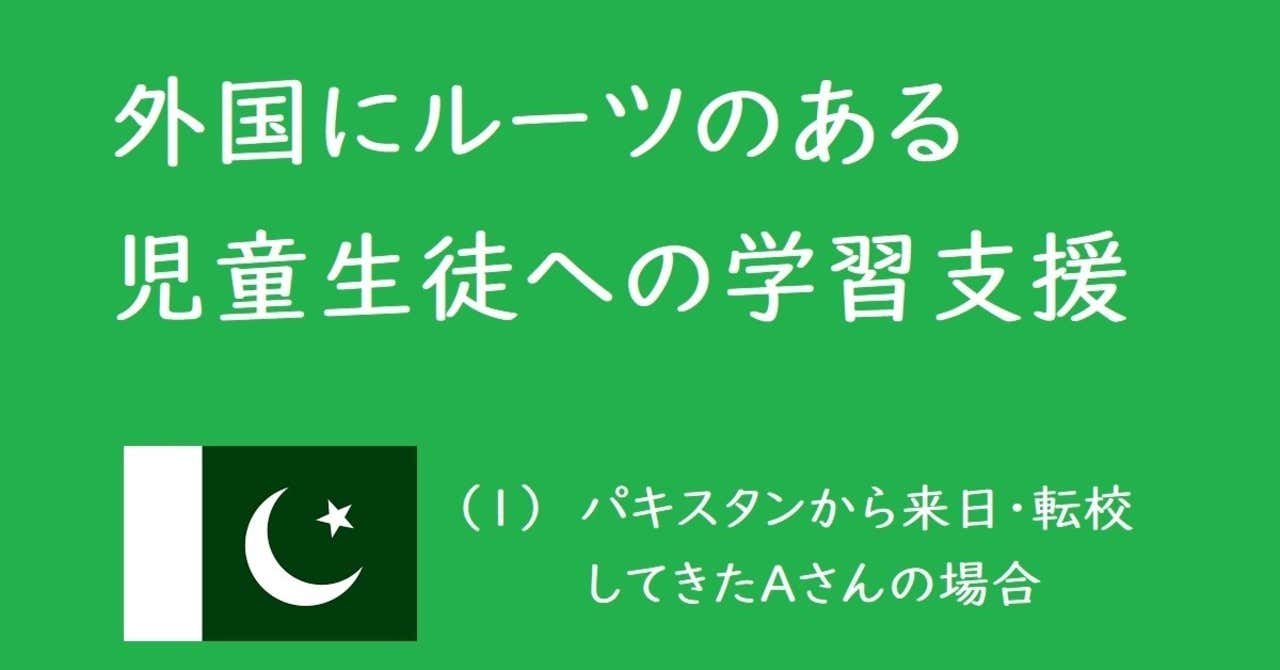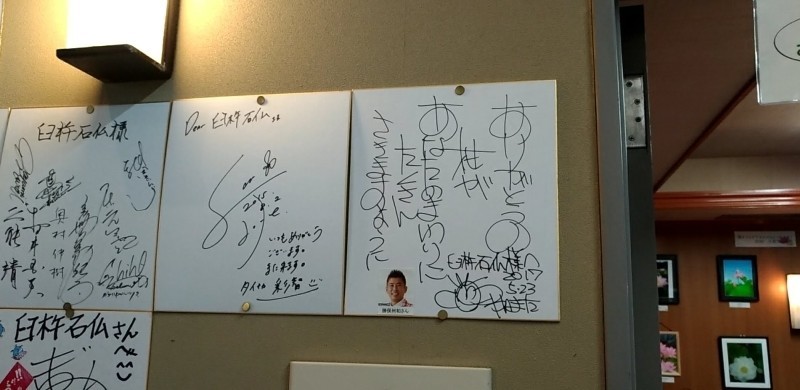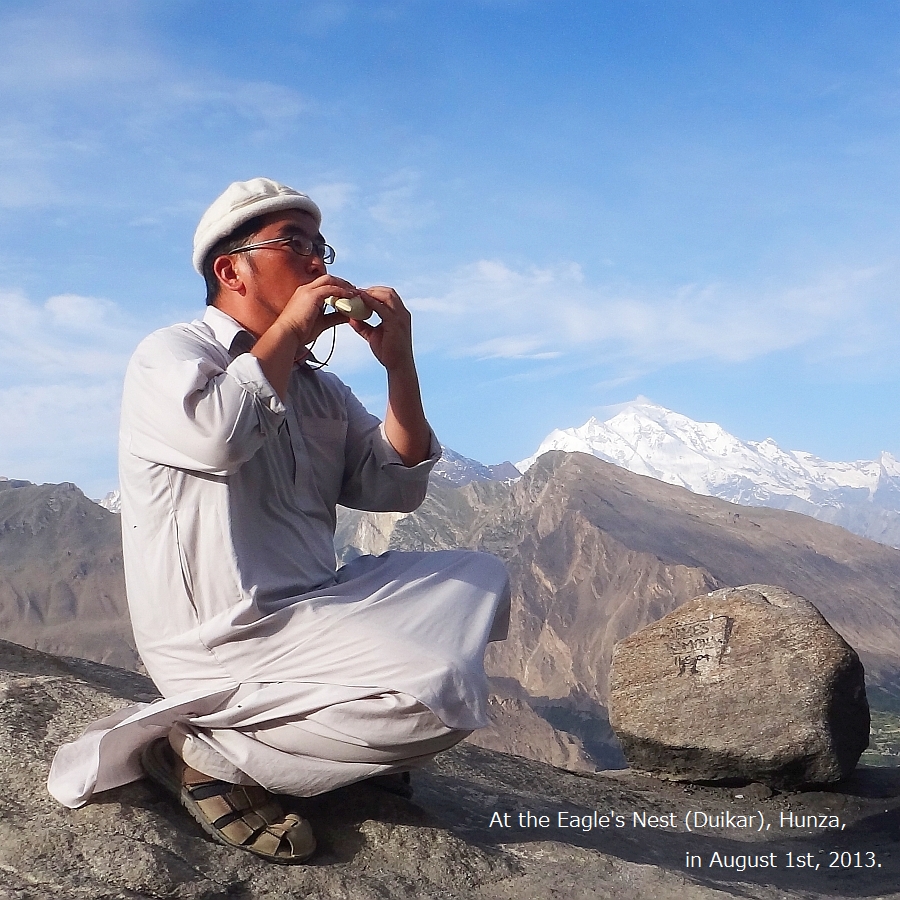Aさんの中学校は、4月初めの入学式後から休校→自宅学習に。
ですが、各学年、クラスごとに分散して登校する日が設けられました。
Aさんのクラスは、今週月曜日(5月11日)でした。
1クラスを、さらに3つに分けて、別々の教室で、学習課題の提出、新しい課題の配布などが行われていました。
Aさんも指定された11時に登校をしてきました。
スカイプでは10回以上会えていましたので、
久しぶりなんだけど、久しぶりでないような、不思議な感覚でした。
この中学校は、複数の小学校出身の子たちが通います。
小学校の時に同じクラスだった子たちも、
中学校では別々のクラスに分かれてしまいましたが、何人かの子たちとはAさんと同じクラスになりました。
そうした子たちが、この登校日の時も「〇〇ちゃーん、元気?」と来てくれて声をかけてくれていました。
ソーシャルディスタンス、気をつけないと、なんですけど、
安心できる存在が、お互いのそばにいるって、とっても大切なことだよなぁ、彼ら彼女たちを見ていて、改めて思いました。
この日のことを日記形式にした日本語学習を、スカイプでしてみました。
今回は見本で、わたしが文章を作り準備(画像)をしておきました。
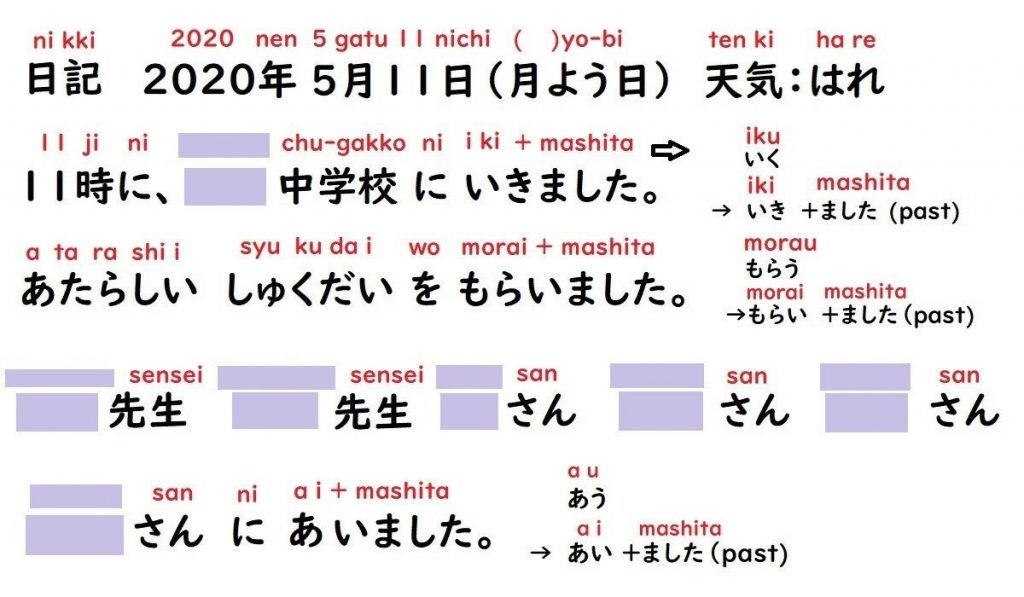
1行ずつ読んでもらって、1つ1つの言葉の意味を確認します。
天気だと、「あめ」は覚えているけれど、「はれ」「くもり」が分からない、など、課題も見えました。
日記だと、自分の経験したことに結びついた語彙が出てくるので、覚えやすいかもなぁ、とも感じました。
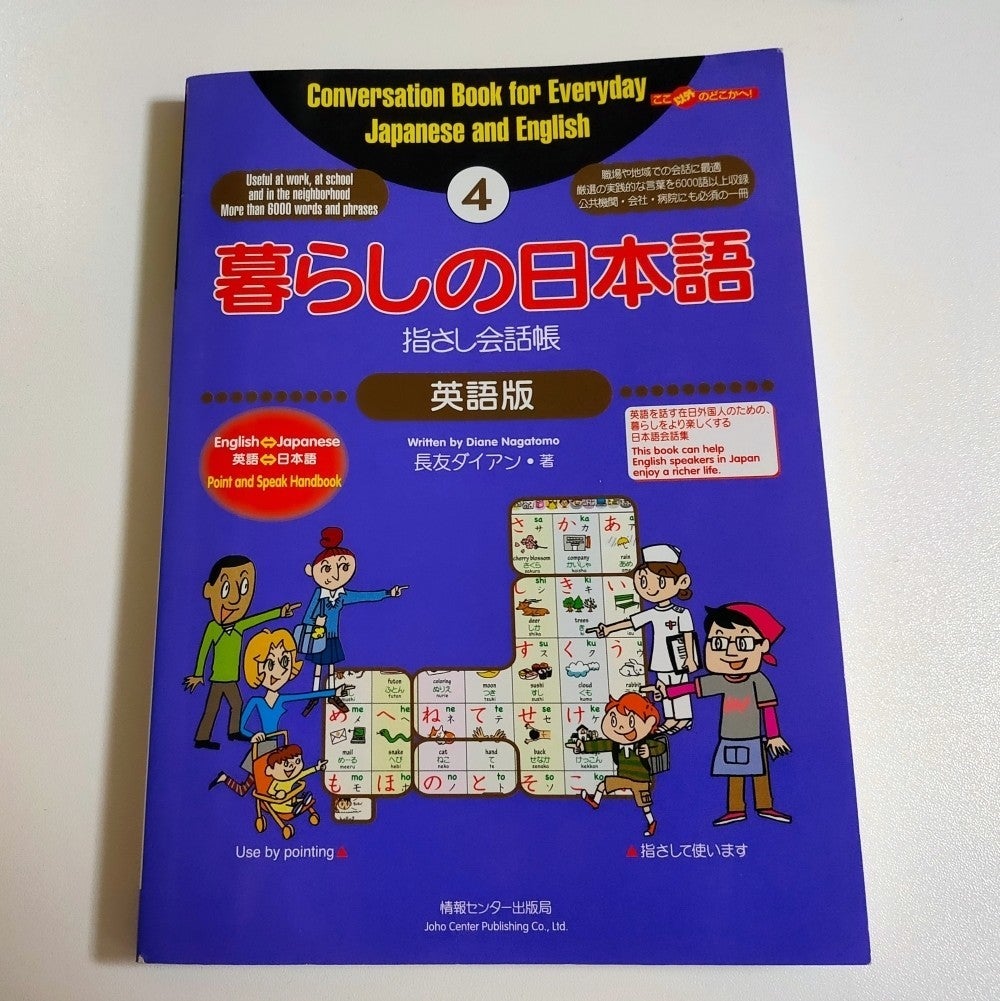
暮らしの日本語指さし会話帳4 英語版 (暮らしの日本語指さし会話帳シリーズ)
https://www.amazon.co.jp/dp/4795838135
1,681円
(2020年05月13日 20:31時点 詳しくはこちら)
身の周りの言葉・表現+辞書がついていて、
日英・英日の単語集がついている、手ごろな会話帳を購入してAさんに。
今日の日記学習で出てきた、
いく iku
もらう morau
あう au
を、Aさんに単語集から探し出してもらいました。
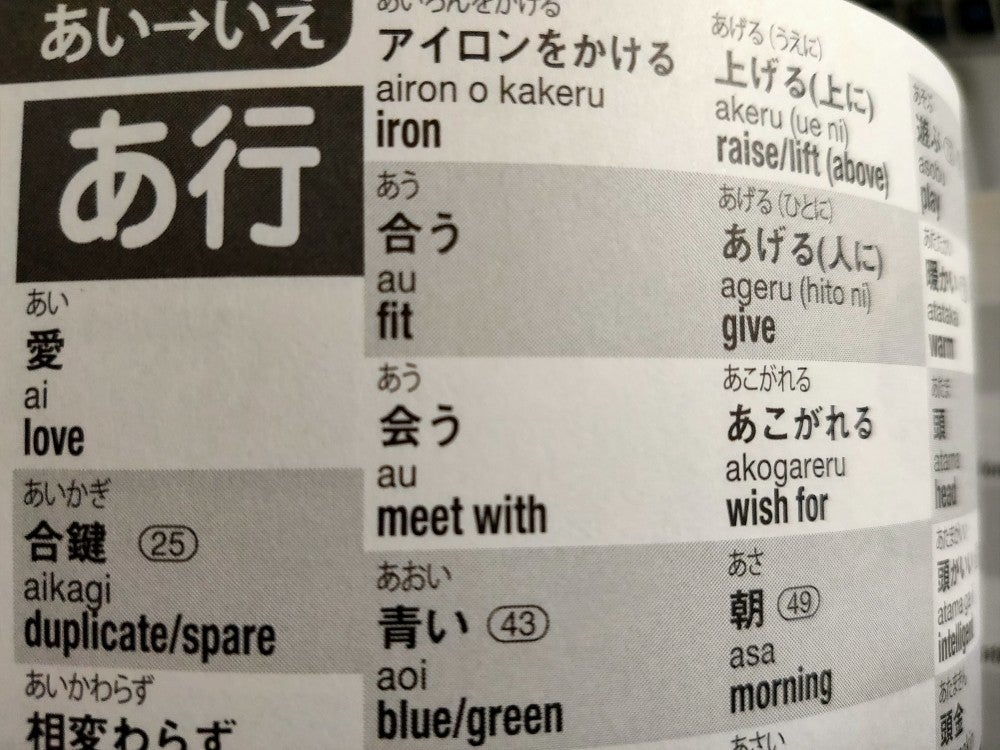
「あう」、だと、「合う」「会う」の発音同じで意味の違う単語があることを説明しました。
ここまでやって30分超。
いつもあくびが出たり、眠そうにしはじめるタイミングです。
がんばれそうなら、もう1課題したいけどなぁ、と思いつつ、
集中力が落ちたら、そこでやめるようにしています。
来週から、登校日がもう少し増える予定。
Aさん、ずっと家にこもっていますから、友だちや先生と会える機会が増えて、中学校にも慣れていってほしいなぁ、そう思っています。